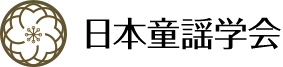童謡について

教育用教材の「唱歌」と、日常生活を綴った「童謡」は、①次世代の子どものために、②対価を求めることなく、純粋に創作されたという共通点がありました。かつて両者を「童謡・唱歌」と総称したのは「次世代の人づくり」という共通目標があればこそだといえましょう。
児童音楽ジャンルの定義
-
🌸わらべ歌
民間伝承による子どもの遊び歌。- かごめかごめ
- 通りゃんせ
- あんたがたどこさ
-
🎓唱歌
教育を目的に創作された児童歌曲。- 蛍の光
- 故郷
- ウミ
-
📚童謡
一流の文学者や音楽家が
情操教育を目的に作った作品- 赤い靴
(作詞:野口雨情/作曲:本居⾧世) - 嬉しいひなまつり
(作詞:山野三郎/作曲:河村光陽) - みかんの花咲く丘
(作詞:加藤省吾/作曲:海沼 實)
- 赤い靴
-
🌈新しいこどものうた
童謡唱歌を否定し
音楽性を重視した児童歌曲- めだかの学校
(作詞:茶木 滋/作曲:中田喜直) - 犬のおまわりさん
(作詞:佐藤義美/作曲:大中 恩) - おはなしゆびさん
(作詞:香山美子/作曲:湯山 昭)
- めだかの学校
-
📺アニメソング
アニメ番組の内容を書き下ろした作品
(※タイアップ作は含まず)- 鉄腕アトム
- 科学忍者隊ガッチャマン
- ドラえもんのうた
-
🎤児童歌謡
子どもに歌わせることを
目的に企画された児童向け合唱曲など- 手のひらを太陽に
(作詞:やなせたかし/作曲:いずみたく) - 旅立ちの日に
(作詞:小嶋 登/作曲:坂本浩美) - にじ
(作詞:新沢としひこ/作曲:中川ひろたか)
- 手のひらを太陽に
童謡の歴史

明治期の「唱歌」が難解で教条的だとして大正期に文学者が興したのが「童謡運動」です。これに賛同した有志の作曲家は、作品の文学性を損なうことなく楽曲として纏め、「童謡」と呼ばれる歌曲が誕生しました。童謡は昭和20年代前半に最盛期を迎えますが、GHQ主導の教育改革や「新しい子どもの歌」を掲げる一部の営利作家に排斥されながら、次第にその存在感を失っていきました。昨今では児童歌曲全般が童謡と総称され、本来の魅力が見失われつつあります。
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 明治5年 (1872年) |
学制発布により学校制度が確立するも、音楽と体育は当初採用されず。 |
| 明治14年 (1881年) |
初の「小學唱歌集」発行。西洋音楽を基にした唱歌が学校教育で導入される。 |
| 明治38年 (1905年) |
夏目漱石が「ホトトギス」で「童謡」を発表。 |
| 大正7年 (1918年) |
鈴木三重吉が童謡雑誌「赤い鳥」が創刊し、多くの文学者が参加。 |
| 大正8年 (1919年) |
日本初の歌曲童謡「かなりや」が発表(西條八十作詞、成田為三作曲)。 |
| 昭和8年 (1933年) |
音羽ゆりかご会が創設され、「赤い鳥童謡運動」の普及活動に従事。 |
| 昭和18年 (1943年) |
NHKが東京放送児童合唱団を組織し、音羽ゆりかご会が委託される。 |
| 昭和20~21年 (1945~1946年) |
川田正子の「里の秋」「みかんの花咲く丘」などが大ヒットし戦後復興に童謡が貢献。 |
| 昭和30年 (1955年) |
ウィーン少年合唱団の来日。「ろばの会」が「新しいこどもの歌」を推奨。 |
| 昭和44年 (1969年) |
日本童謡協会が設立され、童謡文化の再興を目指すも内部分裂が生じる。 |
| 昭和50年代 (1970年代) |
アニメソングやアイドル歌謡が子どもたちの人気を独占。童謡は衰退傾向に。 |
| 平成時代 | バブル期に営利イベントを濫発した「新しいこどもの歌」は衰退の一途へ。 |
| 令和時代 | 平成30年創設の「日本童謡学会」が童謡の本来の意義を取り戻す活動に従事。 |
童謡の歴史と童謡学会の関わり
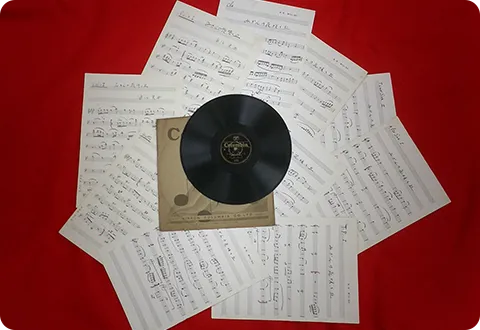
日本童謡学会は2018年に「童謡100年」を機として創設されました。国内で唯一、戦前から活動を継続し、赤い鳥童謡運動を継承するただ一つの童謡団体でもある「音羽ゆりかご会」と連携し、数多くの史料のもと「本来あるべき童謡の姿」とその活用法を研究しています。また同時に、一般向けには「童謡」の正しい歌唱法や創作手法を提供することで、本来の童謡を踏襲する新たな文化醸成にも注力しています。当学会は日本の童謡文化を継承するただ一つの団体です。
-

WEBからのお問い合わせ
-